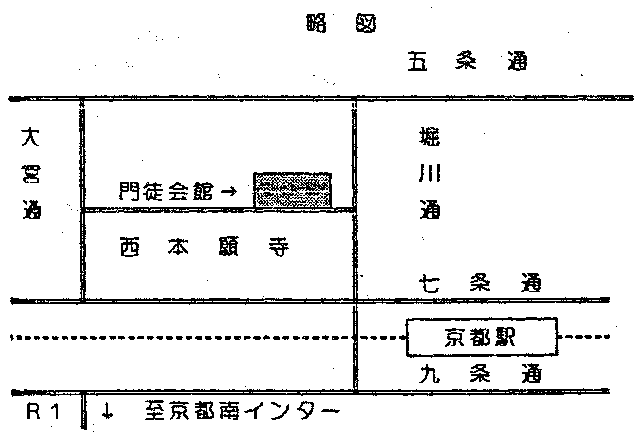|
||||
《 案内 》
第六回部落問題全国交流会にお出かけください
今年も全国交流会の季節がめぐってきました。友人や知人、あるいは手紙のやりとりをしながら顔を合わせていない人と話せると思えば、やはり心がはずみます。 昨年7月30、31日の二日間、京都で開かれた第五回交流会には、各地から200 名をこえる人びとが集り、濃密な議論をかわすとともに、新しい出会いがあったりして大いに交流の実をあげました。これまでになく広範な人びとの参加がみられたばかりでなく、開催直前に京都新聞で紹介されたり、また『朝日ジャーナル』誌(8/12)に“『美しい虹』のイメージに接近する試み-京都・部落差別を「両側から超える」普通の人々の全国交流会”と題したルポが掲載されるなど、その反響の大きさに驚きつつ、いくぶん面はゆい感じがしないでもありませんでした。 それはともかく、交流会の紹介がわりに『こぺる』No.133(89/1) に寄稿した拙文「自らの課題をまさぐる一つの試み」から冒頭部分を抄録します。
この一年、部落解放運動の危機は確実に広がっています。組織や運動への信頼、信用はさらに低下したとみてまちがいない。「冴えない雰囲気」は強まりこそすれ、弱まったとはとうていいえないのではないでしょうか。そうであればあるほど、「部落差別とわたし」「差別とわたし」、さらには「人間と差別」について、より深い思索と討論が求められているように思えてなりません。交流会がそうした場の一つになればうれしい。 ところで第六回交流会の開催要項が別掲のようにきまりました。一切の資格・立場を問いませんので、ぜひともお出かけください。(藤田)
《 第六回部落問題全国交流会「人間と差別をめぐって」開催要項 》
日 時:8月5日(土)午後1時~6日(日)正午.
場 所:京都・本願寺門徒会館(京都市下京区花屋町通り堀川西入る柿本町) 西本願寺の北側.電話075-361-4436. 交 通:京都駅より市バス 9・28・75系統、西本願寺前下車
1時 開会 講演 阿部謹也さん(一橋大学教授) 「西洋中世史からみた人間と差別」(仮題) 3時 分科会 第1分科会 差別とわたし 第2分科会 差別とことば 第3分科会 事業で差別をなくしていいのか 第4分科会 解放運動の主体はだれか 6時 夕食 7時 分科会 9時半 懇親会 8月6日(日) 9時 分科会報告と全体討論 11時半 集会のまとめ 12時 閉会 費 用:7000円(参加費+夕食+宿泊+朝食) 3700円(参加費+夕食) 2000円(参加費) 申込み:〒502 岐阜市長良太平町1-14 太平天国社内「部落問題全国交流会事務局」あて、 葉書か封書に「お名前、住所、tel 、参加ご希望分科会、参加区分 (Ⅰ.夕食+宿泊+朝食 Ⅱ.夕食のみ)」を書いて申込んでください。 電話の場合は0582-41-0964(船坂)まで。 締切り:7月15日(土) その他:*例年通り、各地で発行されたビラ、パンフ、新聞などを多数ご持参ください。 また第一日目夜の懇親会への名産・特産品の持ち込み大歓迎ですので、よろしく。 *なお今回は特に案内状を差しあげません。悪しからず。
《 阿部謹也さんの本を読む 》②
『刑吏の社会史-中世ヨーロッパの庶民生活』(中央公論社.新書No.518.1978 )
|
||||
|
津田ヒトミ(熊本)
|
||||
|
1.
阿部氏の数多い著書の中から、何か一つ感想文をといわれて、最も新しい著書『中世の罪と罰』についてと、最初は考えていたが、もう一度考え直して、よく知られている『刑吏の社会史』をとりあげることにした。
その理由の一つは、昨年八月の全国交流会の夜の懇親会の場で、とある人に刑吏について意見を求められたことによる。 それは、わたしが昼間の分科会で、父の仕事でもあった「屠殺」についてのこだわりに触れたからだったようだ。 わたしの中で、ある意味で、忌まわしい響きさえもつと感じられていた「屠殺」について、数年間わたしはとらわれ続けてきたのだった。そのことについての、その後のわたしなりの新たな展開は別の機会に譲るとして、その人はその時、「動物ならまだいい」といったのだった。 その場でわたしは、何等かの、はっきりしたわたしなりの意見を述べることも出来ず、その人と一年後の再会を約して別れた。 もちろん、阿部謹也氏の『刑吏の社会史』はずっと以前に読んでいたが、とっさに何かがいえるほど、読み込んでいたわけでもなかった。 同じ年の秋に、日本での死刑廃止の運動を進めている団体のパンフレットを見る機会があり、その中でいかなる犯罪も、人が人を死に至らしめる道理がないという主旨と、もう一つ、元死刑執行人の聞き取りで、死刑執行人がその仕事ゆえにもつ苦悩の一部が語られる中で、その人たちの心の傷や、「ストレス」というものはまさに死刑制度の中でつくられたものだと、伝えていた。 時をほぼ同じくして、NHKで放映されたアメリカかどこかの死刑囚の二十四時間を追ったドキュメントの再放送を視て、わたしはもう一度『刑吏の社会史』を手にとった。
2.
「このような特定の職業の担い手が、差別の対象とされ、賎民視された地域は、ヨーロッパに限らず、アフリカ、インド、中国、日本などに類似の現象がみられる」とした上で、中・近世ヨーロッパ史をみていく中で「私たちは常に世界史的視野を持っていなければならない」とする阿部氏のこの著書は、日本における刑吏について考える上で必読書であると思えたのだった。
『刑吏の社会史』を参考にして、刑吏について考えてみると、大ざっぱにいっていくつかのポイントをあげることができる。 一つは賎視され、差別されたその個々の形態について、もう一つは処刑の諸相とそれに関わる刑の執行人たちについて、そしてさらにもう一つは、「刑罰なき時代」から、都市の成立という時代の中での刑吏の登場と、その罪と罰の変遷についてである。 とりわけ、わたしが興味を持ったのは、各々の処刑の様相と、それに関わる刑吏たちの姿であった。 結局わたしは、その一つ一つに対して、何等かの心理的動揺や、ストレスを感じていたんでは、仕事として成り立たないだろうと、父のしてきた「屠殺」というものについて考えはじめていて、そう思ってみれば「たった一発で苦しませずに殺さんといかん」と話していた父の言葉に、うしろ暗さなどは露ほどもなく、むしろそうできる自分の「技術」を自慢していたようなことが思い出された。 そして、中世ヨーロッパの刑吏たちが、「ツンフトの職人たちが自分の職業に専念し、職人としての誇りを技術を磨く中で培っていたと同じように、職人としての誇りを持っていた」もので、「一撃で頚骨のわずかの隙間に剣をふりおろせるだけの芸術ともいえる技術を身につけていなければならなかった」という時、彼らが「極度の賎視と蔑視の中にあって、…職業人としての誇りを持ち続けようとした」ことに、父の言葉にみる共通の「光」とでもいうようなものを見い出さずにはいられなかった。 そしてそのことはまた、今、私たちがパックに入った細切れの肉を食する時、およそ「命」というものと向き合えないような食文化の中で、父のしてきた仕事をその実態(実体)としてみることなく、忌わしいイメージだけが先行するように、阿部氏は刑吏について、「都市空間の成立によって…犯罪がその社会の共同責任であるという考えが極度に薄れ」「一人でその社会の歪みの全体を背負い、断罪され、刑場の露と消えてしまう」場合、「人々は自分とは関わりのない出来事として、その日の仕事に埋没していく」中で、「おそらく潜在意識の底では…自分とは無関係ではないことを知っていたが故に、…それをおそれ、そのおそれが蔑視ととして澱んでいったのであろう」と結んでいる。
3.
わたしがここで取り上げたことは、この本の一部分にしか過ぎず、全体として示唆を与えてくれる重要なところは他に多々ある。
キリスト教以前のゲルマン社会においては、処刑は犯人を死に至らしめるものではなく、一つの儀式であった。そこでの刑吏の役割は、祭りを司る者であったことがうかがえるし、死に至らしめる刑の執行は、むしろ偶然刑であって、例えば一刀打に斬首できなければ、その受刑者は助けられたということなども興味深い。 「かつて処刑は違法行為によって社会が受けた傷を住民が全員で癒すための儀式であった」のが「新しい都市法に於いては犯罪の行為よりも、犯罪者の方に目が向けられはじめ」「犯罪に対しても、呪術による社会の治癒から、個人の責任の糾明へと進み」「いわば刑吏は国家権力による露骨な裁判権の行使に対する人々の不満のはけ口となっていった」という刑吏の存在もそうであるが、共同体やそこでの「罪」や「罰」についての考え方も示唆するものが多い。 最新の著書『中世の罪と罰』に期待するものが大きいが、この『刑吏の社会史』一冊をとってみても、丁寧に幾度も読めば読むほどに、中・近世史のヨーロッパの刑吏というミクロなものが、今の私たちにとって、部落問題や差別を考えていくうえでの重要な手がかりとなるに違いない。
コメント.
『刑吏の社会史』については、わたしも10年ほど前に拙い紹介文を書いたことがありますので、抄録しておきます。
「差別事象、あるいは差別事件の奥にあるものをつきつめてゆくと、社会という“えたいのしれない怪物”と人間の関係、人間の意識、観念の核みたいなものにぶつからざるをえない。そして最後には、きわめて単純なことながら、なぜ人は差別の意識、観念をもつのかという問題につきあたる。/もちろん、この問題にたいして階級社会一般の特性だという説明があり、また支配階級によって支配のイデオロギーとしての差別意識(観念)が注入されるのだという解釈やこの階級社会には差別のイデオロギーが「空気のように」充満しているからだという解釈がなされている。/けれどもこれらの説明、解釈は、あまりにも大ざっぱすぎて説得力にかけるように思う。歴史の刻印をおびた差別意識(観念)が長い時間のトンネルを通って二十世紀末の今日もなお生き生きと人びとをとらえているのはなぜなのか、その秘密を明らかにすることは、とりもなおさず差別からの解放への道すじをどうつけるかということにつながるのだが、運動の中ではあまり関心が払われているようにはみえない。むしろこの秘密解明の努力は、個々の研究者の手にゆだねられ、運動とは離れたところで大きな成果をあげつつある。たとえば日本中世史における横井清さんの仕事(『中世民衆の生活文化』東大出版会)やヨーロッパ中世史における阿部謹也さんの仕事(『ハーメルンの笛吹き男』平凡社)がそれである。/横井さんや阿部さんの仕事に共通しているのは、差別の問題を当時の民衆の生活と意識(観念)のありようとつなげて考えるということである。体制とか支配階級の政策という概念をもち出せば、なにごとか説明されたように思いがちだが、体制というのは人間がつくっているものだし、政策というのも具体的な存在としての人間を通してのみ機能するのだから、人間のありようとその思いをぬきにしてはなにごとも説明されはしない。これは考えてみればあたりまえのことなのである。しかし横井さんや阿部さんの仕事がわれわれに新鮮に映るのは、われわれの方があまりにも既成の概念に身をゆだねすぎてきたからであろう。…阿部さんのこの本は、差別のルーツさがしに終わることなく、民衆の意識の中にある賎視とそれを形成した社会的背景にまでわけいって分析している。賎民身分が先か賎業が先かといったところでの議論ではない。民衆をもとりこむ賎視のありようを歴史の流れの中に位置づけようとする阿部さんの仕事は差別意識(観念)の問題を考える上で大きな示唆を与えてくれよう。…」(『紅風』No.16. 1978/12)
《 あとがき 》
*今号は交流会の案内をかねていますので、急いで発行しました
*次回『阿部謹也さんの本を読む』は柴田則愛さんによる『中世賤民の宇宙』です *毎日新聞(6/3.大阪本社版)の「部落解放文学賞の選者-井上、野間両氏が辞退-小説部門受賞者への処遇に反発」という見出しの記事が目にとまりました。受賞者がその属する県連の方針に反対して処分を受けていたために、部落解放同盟全国大会での授賞式の出席を辞退させられていたことが、井上光晴さんや野間宏さんの選者辞退のきっかけとか。「県連から処分を受けている鈴木さん(受賞者)が出席し会場が混乱すれば、鈴木さん自身にキズがつくと考えて取った措置」との寺本知実行委員長の説明はいかにも苦しい。組織・運動の論理といえばそれまでだけれど、こんなことでいったいどうなるのだろうかと気になります *北京の学生、市民に発砲する人民解放軍の姿をテレビで見ながら、しきりに魯迅の「花なきバラの二」(1926.3.)を憶い出していました。軍閥政府による天安門前での学生虐殺(死者47、負傷者150 名以上)に対し、魯迅は「もし、かくのごとき青年を殺し尽くしたとするも、屠殺者もまた断じて勝利者とはなり得ぬことを知らねばならぬ。中国は、愛国者の滅亡とともに滅亡するであろう。…もし中国が、なお滅亡に至らぬとすれば、将来のことがかならず屠殺者の予想外に出るであろうことを、已往の史実が私たちに教える───これは事件の結末ではない。事件の発端である。墨で書かれた虚言は、血で書かれた事実を隠すことはできない。…威力もそれを抑えることができない。なぜならば、それはもはや、騙されもしなければ、打ち殺されることもないからだ。三月十八日、民国以来のもっとも暗黒なる日に記す」と書きとめていますが、軍閥政府の蛮行が人民共和国の名によって、より大規模に再現されるとは。暗澹たる気持になっています(6/6) *6月2日、大阪の方からカンパ5000円をいただきました。多謝 *本『通信』の連絡先は〒501-11 岐阜市西改田字川向 藤田敬一です。 |